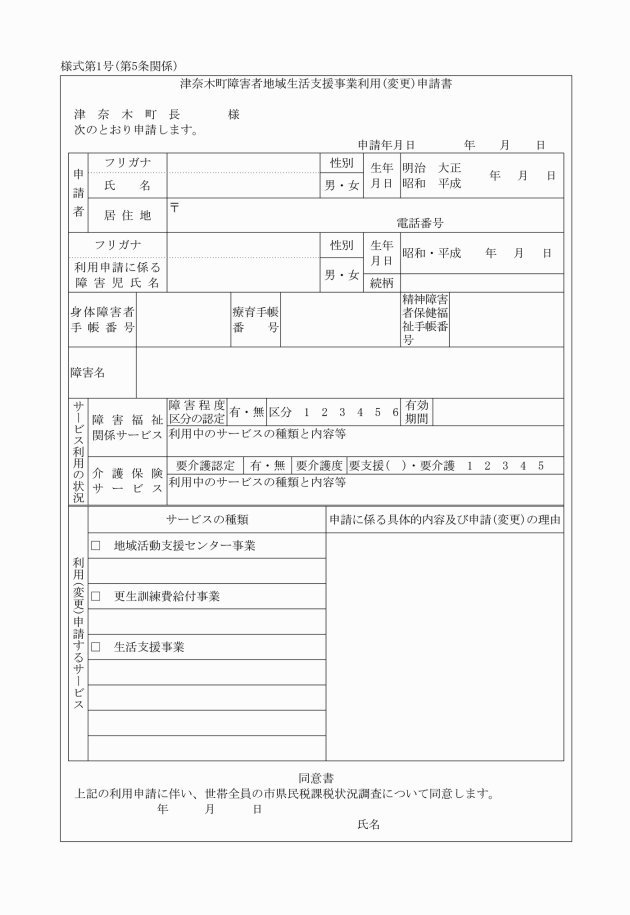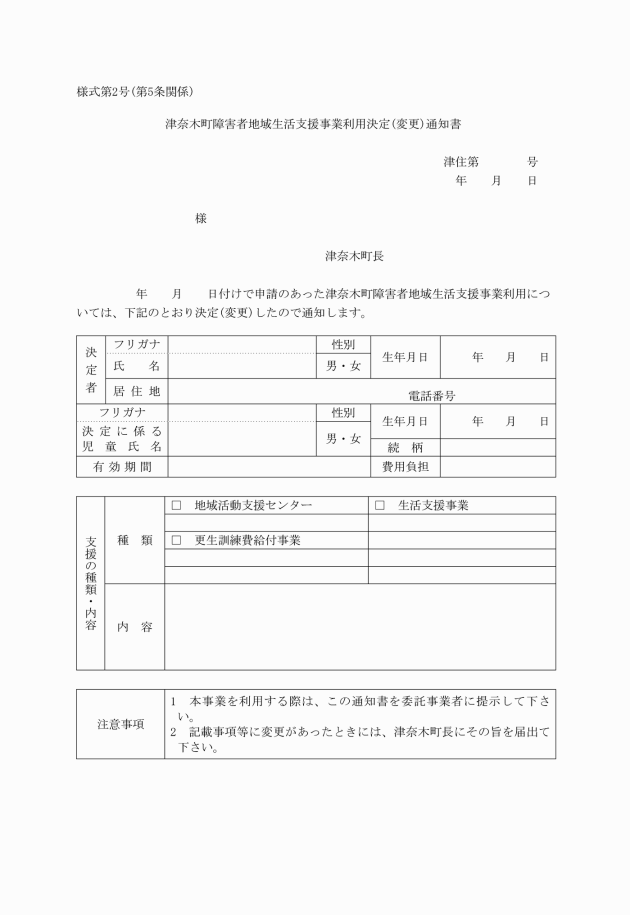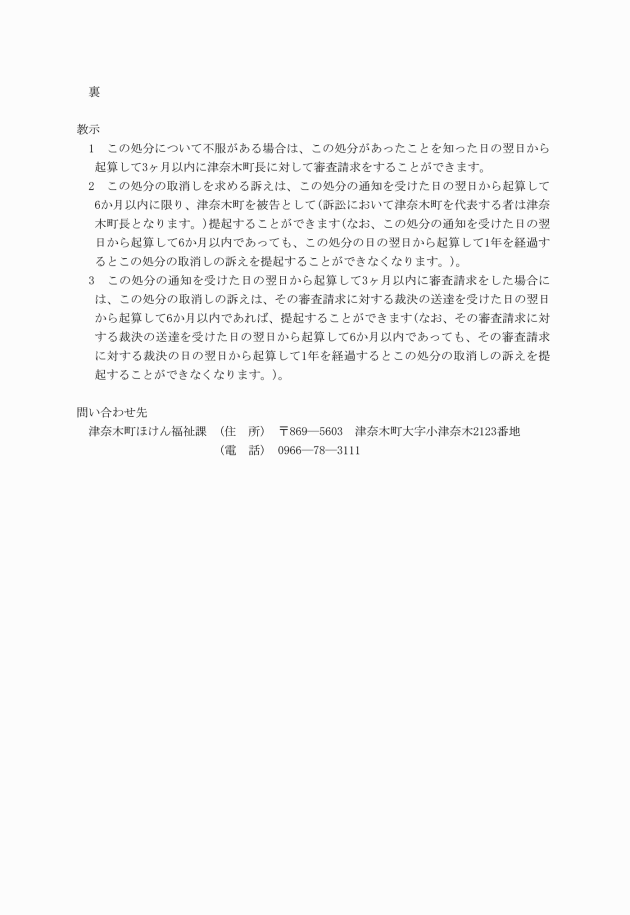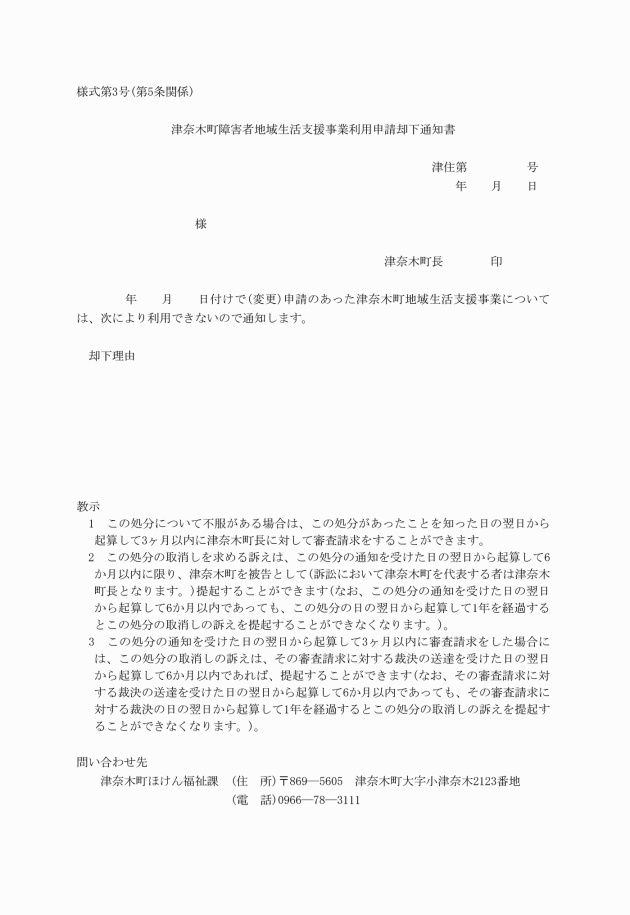○津奈木町地域生活支援事業実施要綱
平成18年10月11日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同法第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は津奈木町とする。ただし、必要に応じ圏域市町による共同実施ができるものとする。
2 町長は、事業の運営の一部又は全部を、適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、原則として本町に居住する65歳未満の障害者等とする。
(事業の内容等)
第4条 この事業の内容は、別記のとおりとする。
(事業運営)
第5条 町は、利用対象者の選定に当たって、相談支援事業者、地域自立支援協議会、障害福祉に係る各関係機関を活用する等実情に応じて判断するものとする。
3 町又は委託先は、この事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
4 町は、この事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行う当該事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
5 この事業の一部を委託して実施する者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町に報告するものとする。
6 町は、地域住民に対し、この事業の周知を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(津奈木町心身障害児(者)地域療育推進事業実施要綱の廃止)
2 津奈木町心身障害児(者)地域療育推進事業実施要綱(平成13年告示第19号)は、廃止する。
附則(令和6年3月19日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記(第4条関係)
障害者地域生活支援事業
(1) 障害者相談支援事業
① 目的
障害者相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
② 事業概要
障害者の福祉に関する各般の問題につき、障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者の権利擁護のために必要な援助を行う。
③ 事業内容
(ア) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(イ) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(ウ) 社会生活力を高めるための支援
(エ) ピアカウンセリング
(オ) 権利の擁護のために必要な援助
(カ) 専門機関の紹介
(キ) 地域自立支援協議会の運営等
(2) 福祉ホーム事業
① 目的
現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
② 対象者
家庭環境、住宅事情の理由により、居宅において生活することが困難な障害者。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。
③ 利用方法
福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。
④ 管理人の業務
(ア) 施設の管理
(イ) 利用者の日常生活に関する相談、助言
(ウ) 関係機関との連絡、調整
⑤ 留意事項
(ア) 利用者の健康管理、レクリエーション、非常災害対策については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。
(イ) 疾病により利用者が生活に困難を生じた場合には、関係機関に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(ウ) 利用者の守るべき共同生活上の規律、その他必要な事項については、利用者の意見を尊重して定めること。
(3) 更生訓練費給付事業
① 目的
法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
② 支給対象者
法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
③ 支給額
訓練の内容を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算した額とする。
④ 代理受領
更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は支給決定者から必ず支給申請手続き及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
また、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、施設長は、支給決定障害者に対してこれらの物品の購入に努めるよう指導すること。
(4) 地域活動支援センター事業
① 目的
障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動及び生活活動の機会の提供自活に必要な訓練を行うとともに、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活の促進を図ることを目的とする。
② 事業内容
基礎的事業は、支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。
基礎的事業に加え、本事業の機能強化を図るため、以下の事業を実施する。
(ア) 地域活動支援センターⅠ型
専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発の事業を実施する。
(イ) 地域活動支援センターⅡ型
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴サービスを実施する。
(ウ) 地域活動支援センターⅢ型
ア 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体が実施する通所による援護事業(以下「小規模作業所」という。)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている。
イ このほか、自立支援給付に基づく事業所に併設して実施することも可能である。
③ 職員の配置
本事業を実施するに当たって事業所は、次に掲げる各号のとおり職員を配置しなければならない。
(ア) 基礎的事業
職員配置は、1名以上とし、うち1名は専任者とする。
(イ) 地域活動支援センターⅠ型
基礎的事業による職員のほか1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
(ウ) 地域活動支援センターⅡ型
基礎的事業による職員のほか1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。
(エ) 地域活動支援センターⅢ型
基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。
④ 利用者数
本事業に当たっては、次に掲げる各号のとおりの利用者数とする。
(ア) 地域活動支援センターⅠ型
1日当たりの実利用人員が概ね20名以上。
(イ) 地域活動支援センターⅡ型
1日当たりの実利用人員が概ね15名以上。
(ウ) 地域活動支援センターⅢ型
1日当たりの実利用人員が概ね10名以上。
⑤ 利用者の負担
本事業に係る経費は、利用者の自己負担とする。その際利用料は、直接設置主体が徴収することができるものとする。
⑥ 留意事項
支援センターは、次の各号に留意して実施するものとする。
(ア) 運営主体は、本事業の利用者との間に、本事業の利用に関する契約を締結すること。
(イ) 地域活動支援センターの事業を実施する者は、法人格を有していなければならないこと。
(5) 理解促進研修・啓発事業
① 目的
理解促進研修・啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、研修・啓発を通じて町民への働きかけを強化することにより、障害者等への理解を深め、共生社会の実現を目的とする。
② 事業内容
理解促進研修・啓発事業は、次に掲げる方法で実施するものとする。
(ア) 教室等の開催
障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病等)並びに、手話、介護等の実践及び障害特性に対応した福祉用具等の使用方法等に対する理解を深めるための教室等を開催する。
(イ) 事業所訪問
町民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や障害者等との交流により必要な配慮、知識及び理解を促す。
(ウ) イベント開催
有識者による講演会、障害者等との交流イベント等、多くの町民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。
(エ) 広報活動
障害特性を解説したパンフレットやホームページ等の作成により、障害者等に対する正しい知識の普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。
(オ) その他の方法
前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な方法により実施する。
(6) 自発的活動支援事業
① 目的
自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を目的とする。
② 事業内容
自発的活動支援事業は、次に掲げる方法で実施するものとする。
(ア) ピアサポート
障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を実施する。
(イ) 災害対策
障害者等を含めた地域における災害対策活動を実施する。
(ウ) 孤立防止活動支援
地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を実施する。
(エ) 社会活動支援
障害者等が、仲間と話し合い、自らの権利や自立のため社会に働きかける活動(ボランティア等)や、障害者等の社会復帰活動を支援する。
(オ) ボランティア活動支援
障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。
(カ) その他
前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な方法により支援する。
(7) 成年後見制度法人後見支援事業
① 目的
成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保するための体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
② 実施内容
成年後見制度法人後見支援事業は、次に掲げる方法で実施するものとする。
(ア) 法人後見実施のための研修
法人後見実施団体又は法人後見の実施を予定している団体等に対し、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成し、実施するものとする。
(イ) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
法人後見の活用等のための地域の実態把握及び法人後見推進のための検討会等を実施する。
(ウ) 法人後見の適正な活動のための支援
弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制を図る。
(エ) その他
前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な方法により支援する。